未来へ続くおいしさを

CHARACTERS
ノースカラーズ村の仲間たち
ここには、北海道に住んでいる動物たちが暮らしています。
さあ、どんな仲間がいるのかな?
 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo
動物の写真、生態や特徴についての説明内容については、
旭川市旭山動物園に協力をいただいています。※一部を除く
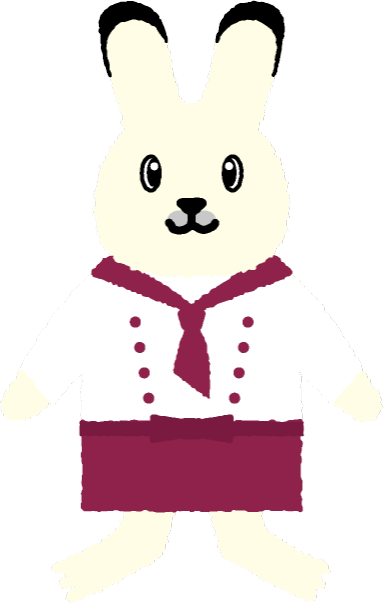
エゾユキウサギ
なまえ:シーナ
冬になると毛が真っ白になるシーナは、
ちょっぴり恥ずかしがり屋のパティシエです。
オーガニック原料や安心できる素材をあつめるのが大変だけれど、
みんなの笑顔を思い浮かべながら、心を込めてお菓子を作っています。
お菓子作りのアイデアが浮かぶと、耳をピンと立ててワクワクしています。

- 学名
- Yezo Lepus timidus ainu
- 英名
- Mountain Hare
- 分類
- ほ乳綱ウサギ目ウサギ科
- サイズ
- 頭胴長:50~58cm
- 体重
- 2.0~3.9kg
- 寿命
- 約10年
エゾユキウサギについて
冬には真っ白な毛になり、夏は茶色の毛になります。夏毛の時期にはふつう夜だけ活動し、冬毛の時期は、エサが少ないため、昼間も採食活動をし、雪に埋もれた植物を掘り出したり、木の枝や芽をかじったりします。また、かんじきのような大きな足で、やわらかい新雪の上でも埋まらずに駆け回ることができます。足の裏には密生した毛があり、すべり止めにもなっています。
動きはとても素早く、常に警戒しています。日中は見えないところに隠れていることが多いです。

エゾシカ
なまえ:まめ
パン作りが大好きなまめは、森のパン屋さんを切り盛りしています。
毎朝、じっくりと生地をこね、ふんわりと焼き上げるパンは、
村のみんなに大人気。
できるだけシンプルな材料で、素材の味を生かしたやさしいパンを作ることを心掛けています。
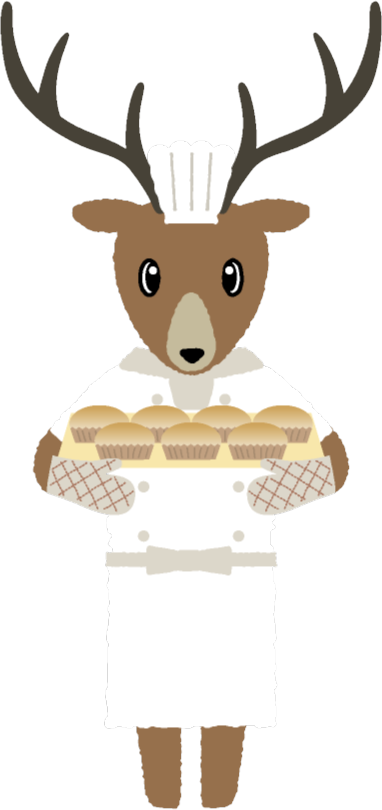
エゾシカ
なまえ:エリック
大きなツノが素敵なエリックは、まめと一緒に村のパン屋さんをしています。
エリックは、無駄を出さずにパンを焼くことがとっても得意!
村のみんなが食べきれる量を計算しながら、毎日ちょうどいい分だけを焼いています。
もっちりふわふわのパンは、エリックとまめの自慢の一品です。

- 学名
- Cervus nippon yesoensis
- 英名
- Hokkaido Sika Deer
- 分類
- ほ乳綱 偶蹄(ウシ)目 シカ科
- サイズ
- 頭胴長:150~190cm
- 体重
- 80~130kg
- 寿命
- 約15年
エゾシカについて
夏毛は茶褐色に白い点々の模様があり、シカの仲間でも特に美しいです。冬毛は白い点々の模様が消え、灰褐色になります。角はオスだけが持ち、毎年春に自然に落ちます。そして、春から初夏にかけて新しく伸び、秋には角は堅くなり完成します。
旭川は四季がはっきりしている場所です。旭山動物園のエゾシカも、四季によってそれぞれ表情や体つきがまったく違い、エゾシカを見ると季節を感じることができます。そんな北海道の身近な動物であるエゾシカを肌で感じてみてください。

エゾリス
なまえ:ハンナ
冬になると耳の毛がふさっと伸びるエゾリスのハンナ。
村のカフェで働いています。後で食べようとこっそりナッツを隠しますが、隠したことを忘れがちなおちゃめんさん。ふわふわの尻尾を器用に使いながら、たくさんのカップを運ぶ姿は、カフェの名物になっています。

- 学名
- Sciurus vulgaris orientis
- 英名
- Yezo Red Squirrel
- 分類
- ほ乳綱 げっ歯(ネズミ)目 リス科
- サイズ
- 頭胴長:22~23cm
- 体重
- 300~470g
- 寿命
- 約2~3年
エゾリスについて
北海道の森林にのみ分布し、農家周辺や公園の林でも見られるため、よく知られた動物です。四肢の指には、長いかぎ爪があり、木の幹を上下左右に移動できます。また、ふさふさした毛が生えた長い尾は、樹上で移動する際にバランスをとるのに役立っています。また、夏毛・冬毛の違いもあり、季節を感じられる動物です。
旭山動物園では、檻や木を上下左右に動き回る姿が見られます。その動きはとてもすばしっこく、目で追いかけるのも大変です。姿が見えないときは、巣箱の中で休んでいることが多いです。

エゾシマリス
なまえ:まあさ
おしゃべり好きなまあさは、村の果物屋さんです。
たくさんの果物に囲まれておしゃべりをしている時間が幸せです。「今日のおすすめはこれ!」と元気に紹介しながら、お客さんとのおしゃべりに夢中になることも。村のみんなにフレッシュな果物と笑顔を届ける、太陽みたいな存在です。

- 学名
- Tamias sibiricus lineatus
- 英名
- Siberian Chipmunk
- 分類
- 齧歯目リス科
- サイズ
- 頭胴長(鼻先から尻尾の付け根まで)
12~15cm
尾長 11~12cm
- 体重
- 71~116g
- 寿命
- 飼育下で約9年
(数値は「日本動物大百科Ⅰ 哺乳類Ⅰ」より引用)
エゾシマリスについて
北海道の平地から高山の様々な森林に生息し、地上と樹上で行動します。
背部に5本の黒い縞模様があり、頬袋を持っています。
秋になると地下に作ったトンネル状の巣に食物を貯蔵し、半年という長い間冬眠します。

エゾヒグマ
なまえ:ジャック
大きな体がたくましいジャックは、野菜を育てる農家さんです。ジャックの野菜はどれも元気いっぱい!・・・しかし最近は、暑すぎたり寒すぎたりする気候の変化に悩まされることも。野菜を育てるのはとっても大変なのです。みんなの笑顔のために、おいしくなぁれと毎日がんばってお世話をしています。

- 学名
- Ursus arctos yesoensis
- 英名
- Yezo Broun Bear
- 分類
- ほ乳綱 食肉(ネコ)目 クマ科
- サイズ
- 頭胴長:200~280cm
- 体重
- 100~300kg
- 寿命
- 約25年
エゾヒグマについて
エゾヒグマは現在、生息域の縮小と環境の悪化、過剰な捕殺が衰退をまねき、将来は決して明るいものではありません。エゾヒグマの存続のためには、人間側の意識の変革が必要であり、被害発生を未然に防ぐ保護管理策と生息域の保全の必要があります。
がっしりとした四肢に長い爪、がんじょうなあごと歯をもち、人間のようにかかとを地面につけて歩く、日本最大の陸生動物です。また、木に登ることができます。メスの「とんこ」は、柵に登ったり、プールに入り、窓の所に体当たりをしたり、結構やんちゃなことをして、みなさんを驚かせています。
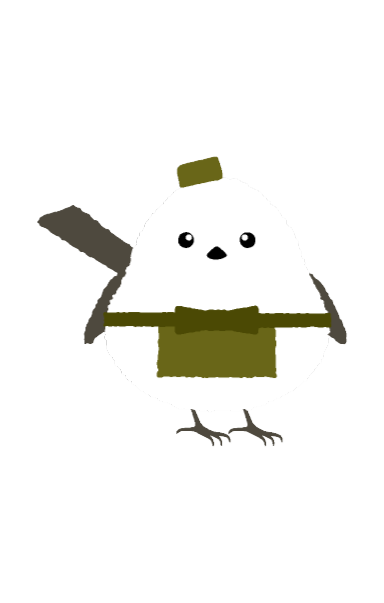
シマエナガ
なまえ:こまる
丸くてふわふわモコモコの姿が愛らしいシマエナガのこまる。
性格はとってもほんわかしています。実家の和菓子屋で修業を始めたけれど、今日もあんを炊く香りにうっとりウトウト・・・。いつか、村の伝統を受け継ぐ立派な和菓子職人になることを夢見ています。

- 学名
- Aegithalos caudatus japonicus
- 英名
- Long-tailed Tit
- 分類
- スズメ目エナガ科エナガ属
- サイズ
- 13~14cm
- 体重
- 5.5~9.5g
- 寿命
- 約4年
(分類は「日本鳥類目録改訂第7版」より引用)
シマエナガについて
真っ白で丸く小さな体とつぶらな瞳がとってもキュートな小鳥、シマエナガ。「雪の妖精」とも呼ばれ、巷で大人気です。エナガの亜種であるシマエナガは北海道にしか生息していない野鳥です。本州以南のエナガには目の上に眉毛のような黒い模様がありますが、北海道に棲むシマエナガの顔には模様がなく真っ白なのが特徴です。平地から山地の林、市街地の公園などに生息し、全道各地の森林で普通に見られます。
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用)

キタキツネ
なまえ:ロウ
ふわふわとしたしっぽを持つロウは、キッチンカーの運転手さんです。
毎日欠かさずキッチンカーを走らせて、体にやさしいお菓子を村のみんなに届けています。
新しいお菓子を届けられるように、レシピ研究もがんばっています。
心を込めて作ったお菓子やパンをみんなに届けるお仕事に誇りを持っています。

- 学名
- Vulpes vulpes schrecki
- 英名
- Red Fox
- 分類
- ほ乳綱 食肉(ネコ)目 イヌ科
- サイズ
- 頭胴長:60~80cm
- 体重
- 2.5~10kg
- 寿命
- 約6~7年
キタキツネについて
キタキツネは現在でも北海道では身近な動物であり、昔から人間とのかかわりが強く、各地の民話や説話にもよく登場する動物です。
毛色は赤褐色で、あごの下から腹部は白色です。四肢の足先全面は黒色で、尾は赤褐色で、先端部に白毛があります。
旭山動物園のキタキツネ展示施設においては、自然の中でひっそりと、あるときは活動的に暮らす様子を観察できる雰囲気となっています。

北海道犬
なまえ:ハル
まじめで勇敢なハルは、ノースカラーズ村を守るおまわりさんです。
雪の中でも行動できるようしっかり体を鍛えていて、パトロールを兼ねたランニングが日課です。
でも、村はいつも平和で事件が起きないので、困った動物のお手伝いがお仕事です。

- 学名
- Canis lupus familiaris
- 英名
- Hokkaido
- 分類
- ほ乳綱 食肉(ネコ)目 イヌ科
- サイズ
- 体高:44~55cm
- 体重
- 15~20kg
- 寿命
- 約12~15年
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より参照)
北海道犬について
北海道犬は、寒さの厳しい北海道の自然環境に適応してきた日本犬の一種です。
古くから北海道のアイヌ民族と共に生活し、狩猟犬として活躍していたといわれております。勇敢で警戒心が強く、主人に対しては非常に忠実です。
体はがっしりとしており、ダブルコートの被毛により雪や寒風にも耐えられます。被毛の色は白・赤・黒・虎・胡麻などがあり、巻き尾と立ち耳が特徴です。
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より参照)

シマフクロウ
なまえ:ホー村長
ノースカラーズ村の長老、ホー村長。
いつも穏やかに村を見守り、困ったことがあれば、静かに話を聞いてくれます。
生態系や食の未来について深く考え、村のみんなが幸せに暮らせるように知恵を伝える頼れる存在です。

- 学名
- Bubo blakistoni
- 英名
- Blakiston's Fish-owl
- 分類
- 鳥綱フクロウ目フクロウ科
- サイズ
- 体長:約70cm
翼開長:約180cm
- 体重
- 約4kg
- 寿命
- 約30年
シマフクロウについて
シマフクロウの「シマ」は北海道に分布しているという意味があります。
世界では最大の大きさとなり、頭部には羽角があり、全身の羽の色は灰褐色で、黒い縦縞模様や横縞が入っています。
河川や湖沼周辺の森林に生息しており、広葉樹大木の樹洞に営巣をし、国内のフクロウの中では唯一魚類を主食とします。他にはカエルなどの両生類や鳥類、小型の哺乳類などを食べます。
個体数は1,500〜4,000羽と推定され、日本では森林伐採による営巣木の減少、河川改修やダム建設による魚類の減少が原因となり、生息数は140羽ほどとなっています。日本では、国指定の天然記念物です。
MESSAGE
メッセージ
“おいしい”とは、誰かの笑顔と幸せが詰まったもの。
“おいしい”には生産者や作り手の想いが込められています。
でも、この“おいしい”を次世代に残していけるのでしょうか。
農業の後継者不足による食料自給率の低下、
気候変動による食料危機、フードロス、食物アレルギー問題。
食をめぐる課題は多く、解決すべきことがたくさんあります。
ノースカラーズ村の仲間たちは、お菓子づくり通して、
“未来へ続くおいしい”を守るために日々奮闘しています。
持続可能な農業の普及と豊かな食文化の発展を願って。
あなたも一緒に、未来へ続くおいしさを考えてみませんか?


